新入社員の皆さんが希望に満ちたキャリアをスタートさせる今、必ず心に刻んでおくべき大事な約束があります。
それが「会社の機密保持」です。
「自分は重要な情報なんて扱わないから関係ない」、「少しぐらいなら大丈夫だろう」といった軽い気持ちが、あなたのキャリアと会社の未来を揺るがす、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があります。
最悪の場合、懲戒解雇(クビ)や多額の損害賠償に発展することも決して珍しくありません。
この記事は、まさに新入社員必見の内容です。社会人として絶対に知っておくべき「会社の機密保持」について、その重要性から具体的な注意点、そして万が一情報を漏らしてしまった場合のリスクまで、分かりやすく解説します。
「知らなかった」では済まされないこの大事な約束を正しく理解し、信頼される社会人としての第一歩を踏み出しましょう。
会社の機密保持とは?社会人としての大事な第一歩

会社の機密保持とは、簡単に言えば「会社の重要な情報を許可なく外部に漏らさない」という、会社と従業員との間の絶対的な約束のことです。これは特定の部署や役職者だけの話ではありません。正社員、契約社員、アルバイトといった雇用形態に関わらず、その会社で働くすべての人に課せられた重い義務なのです。
なぜ新入社員のうちから機密保持を学ぶ必要があるの?
新入社員である皆さんは、まだ社内のどの情報が重要で、どの情報がそうでないかの判断が難しい立場にあります。だからこそ、キャリアのスタート地点である今、機密保持の正しい知識を身につけることが極めて重要になります。
- 信頼の土台作り:機密保持は、会社や同僚、取引先との信頼関係の土台です。この約束を守ることが、社会人としての信用の第一歩となります。
- 無自覚なリスクの回避:悪気なく話した内容が、実は重大な機密情報だったというケースは後を絶ちません。初期段階で学ぶことで、そうした「うっかり」によるリスクを未然に防げます。
- 自分自身のキャリアを守るため:情報漏洩は会社の存続を揺るがすだけでなく、あなた自身のキャリアにも致命的なダメージを与えます。自分自身を守るためにも、正しい知識は不可欠です。
「知らなかった」では済まされない!情報漏洩の大きなリスク
万が一、会社の情報を漏洩させてしまった場合、その影響は計り知れません。「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という言い訳は、ビジネスの世界では通用しないと心に刻んでください。
情報漏洩が引き起こす主なリスクは以下の通りです。
| 影響を受ける対象 | 具体的なリスク内容 |
| 会社 | 経済的な大損失・社会的信用の失墜・競争力の低下・株価の下落 |
| 個人(あなた) | 懲戒解雇(クビ)・数千万円以上の損害賠償請求・刑事罰(逮捕・起訴)による前科・業界内での信用の失墜(再就職困難) |
たった一度のミスが、会社とあなた自身の未来を大きく左右する可能性があることを、強く認識しておく必要があります。
そもそも「会社の機密情報」って何のこと?

「機密情報」と聞くと、特別な文書をイメージするかもしれません。しかし、実際にはもっと身近な情報も含まれます。
法律(不正競争防止法)上の「営業秘密」を参考にすると、一般的に以下の3つの要素を満たすものが機密情報に該当します。
- 秘密として管理されている(秘密管理性): 会社が「これは秘密です」と示している情報(例:「社外秘」マーク、アクセス制限など)
- 事業活動に有用である(有用性): 会社のビジネスにとって価値のある技術上・営業上の情報
- 公然と知られていない(非公知性): 一般に公開されていない情報
新入社員のうちは、判断が難しい場合が多いため、「社内で知り得た未公開の情報は、すべて機密情報である」と考えて行動するのが最も安全です。
これもダメなの?機密情報にあたる具体例
具体的にどのような情報が機密情報にあたるのか、例を見ていきましょう。
顧客情報・取引先情報
会社のビジネスの根幹をなす、非常に重要な情報です。
- 顧客リスト(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)
- 取引先との契約内容、取引価格、仕入れ値、取引履歴
- 商談の内容や進捗状況、提案書の内容
技術情報・ノウハウ
会社の競争力の源泉となる、まさに「宝」とも言える情報です。
- 製品の設計図、仕様書、ソースコード
- 特許出願前の発明内容、研究開発データ
- 独自の製造方法や業務マニュアル、社内研修資料
会社の財務・人事情報
会社の経営や組織の根幹に関わる、特にセンシティブな情報です。
- 未公開の決算情報、売上データ、詳細な事業計画
- M&A(企業の合併・買収)や業務提携に関する情報
- 社員の個人情報、給与、人事評価データ、詳細な組織図
「機密情報」と「個人情報」の違いも理解しよう
機密情報と混同されやすい言葉に「個人情報」があります。この二つの違いを理解しておくことも大切です。
| 項目 | 機密情報 | 個人情報 |
| 定義 | 会社の事業活動にとって有用な、秘密として管理される情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報 |
| 保護対象 | 会社(法人)の利益 | 個人のプライバシーや権利 |
| 例 | 新製品の開発計画、独自の製造ノウハウ、未公開の財務情報 | 氏名、生年月日、住所、マイナンバー、特定の個人の顔がわかる写真 |
顧客リストのように、機密情報であり、かつ個人情報でもある情報も多く存在します。このような情報は、不正競争防止法と個人情報保護法の両面から、特に厳重な取扱いが求められます。
【要注意】情報漏洩はこんな場面で起こりやすい

情報漏洩は、サイバー攻撃のような特別な事件だけで起こるわけではありません。むしろ、社員一人ひとりの「うっかりミス」が原因となるケースが後を絶たないのが現実です。
悪気はなくてもアウト!うっかりミスが招く情報漏洩パターン
悪気のない日常の行動が、重大な情報漏洩につながる危険性を秘めています。新入社員が特に注意すべき3つの場面を紹介します。
SNSへの不用意な投稿
「今日から新しいプロジェクトに参加!頑張るぞ!」といった何気ない投稿が、機密情報の漏洩にあたる可能性があります。
- NG例
- 会社のデスク周りや、PC画面が映り込んだ写真の投稿
- 取引先の社名や、新製品を匂わせる内容の投稿(例:「有名タレントの〇〇さんと仕事した!」)
- 社内の人間関係や愚痴(内部情報が含まれる可能性)
友人や家族との日常会話
仕事の達成感や悩みを親しい人に話したくなる気持ちはわかります。しかし、その会話に機密情報が含まれているかもしれません。
- NG例
- 「今度、有名タレントの〇〇さんを起用したCMを作るんだ」
- 「うちの会社、来月〇〇っていう新サービスを出すらしいよ」
- 「取引先のA社が、業績不振で大変みたいで…」
カフェや電車など公共の場での作業・会話
リモートワークの普及により、カフェや移動中の電車内などで作業する機会が増えましたが、これらの場所は情報漏洩のリスクで溢れています。
- NG例
- 背後からPCの画面を覗き見される(ショルダーハッキング)
- 会社の資料を机に広げたまま離席する
- 同僚と仕事の電話や打ち合わせをする(会話内容が周囲に筒抜けになる)
- セキュリティが確保されていない無料Wi-Fiに接続して重要なデータをやり取りする(通信内容を傍受される危険性)
もし会社の情報を漏らしたら…?「クビ」だけでは済まない厳しい現実
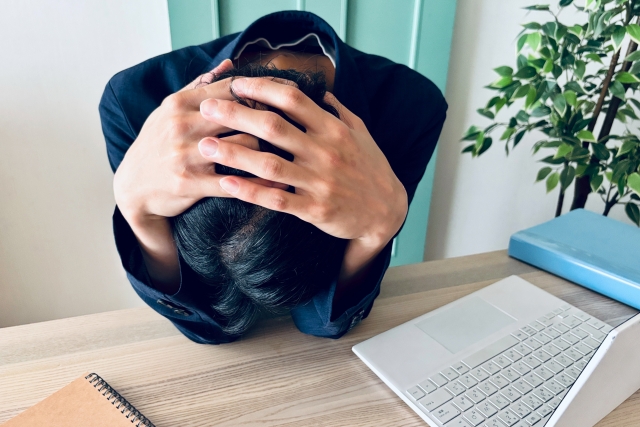
「バレなければ大丈夫」という考えは絶対に通用しません。情報漏洩が発覚した場合、あなたを待っているのは「クビ」だけでは済まされない、非常に厳しい現実です。
会社から受けるペナルティ(懲戒解雇など)
多くの会社の就業規則には、機密情報漏洩に関する罰則規定が設けられています。漏洩の程度や悪質性によっては、最も重い処分である懲戒解雇(クビ)となる可能性が十分にあります。懲戒解雇は再就職の際に極めて不利になる、社会人生命に関わる非常に重い処分です。
多額の損害賠償を請求される可能性
あなたの漏洩行為によって会社が損害を被った場合、会社から民事上の「損害賠償」を請求されることがあります。漏洩した情報の内容によっては、その額は数千万、数億円にのぼることもあり、一生をかけても償えないほどの金銭的責任を負うリスクがあります。
信用失墜だけじゃない!刑事罰に問われるケースも
会社の重要な営業秘密を不正な利益を得る目的で取得したり、他社に漏らしたりする行為は「不正競争防止法」という法律で禁じられています。この法律に違反した場合、「10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金(またはその両方)」という重い刑事罰が科される可能性があります。これは犯罪行為であり、あなたの経歴に「前科」がつくことを意味します。
機密保持は社会人としての「約束」!新入社員が守るべき5つのルール
会社の機密保持は、あなた自身と会社の未来を守るための重要な約束です。今日から実践できる5つのルールを心に刻み、日々の業務に取り組みましょう。
ルール1:入社時の「機密保持誓約書」を正しく理解する
入社時に「機密保持誓約書」や「秘密保持に関する同意書」といった書類に署名・捺印したはずです。これは、あなたが会社の機密保持義務を負うことを法的に約束した証拠です。「よく読まずにサインした」では通用しません。改めて内容を読み返し、自分が何を約束したのか、どのような行為が禁止されているのかを正確に理解しましょう。
ルール2:会社のPCやスマホの取扱いルールを徹底する
会社から貸与されたパソコンやスマートフォンは、会社の重要な情報資産の塊です。私的利用の禁止、複雑なパスワードの厳重管理、ソフトウェアの無断インストール禁止など、会社の定めるルールを必ず守ってください。私物のUSBメモリを安易に接続する行為も、ウイルス感染や情報流出の原因となるため絶対にやめましょう。
ルール3:SNSの利用には細心の注意を払う
プライベートで利用するSNSであっても、あなたは「〇〇会社の社員」です。業務に関する内容はもちろん、会社を特定できるような投稿は一切行わないようにしましょう。公開範囲を友人に限定していても、スクリーンショットなどでそこから情報が拡散するリスクは常に存在します。「SNSは全世界に公開されている」という意識を持つことが大事です。
ルール4:「クリアデスク・クリアスクリーン」を習慣にする
これは、情報セキュリティの基本的な習慣であり、誰でも今日から実践できます。
- クリアデスク:退社時や長時間離席する際には、机の上に書類や資料、USBメモリなどを放置しない。必ず鍵のかかるキャビネットなどに収納する。
- クリアスクリーン:PCから少しでも離れる際は、必ずスクリーンロック(Windowsなら「Win + L」キー)をかける。
この2つを徹底するだけで、物理的な盗難や覗き見による情報漏洩リスクを大幅に減らすことができます。
退職してからも続く「守秘義務」という約束
最後に、非常に大事なことをお伝えします。会社の機密保持義務、すなわち「守秘義務」は、会社を退職した後も続きます。
入社時に署名した機密保持誓約書には、多くの場合「退職後も守秘義務を負う」という条項が含まれています。これは法的に有効な約束です。
「もう辞めた会社だから関係ない」と考えて、在職中に知り得た顧客情報や技術ノウハウを転職先で利用したり、独立開業に活かしたり、友人に話したりする行為は、明確な契約違反・法律違反です。退職後であっても、元勤務先から損害賠償請求や差止請求をされたり、刑事罰の対象となったりする可能性があります。
会社の機密保持は、在職中はもちろん、その会社を離れた後も未来永劫守り続けなければならない、社会人としての重い約束なのです。この約束の重みを理解し、責任ある行動を心がけることが、あなたの輝かしいキャリアを守り、築いていくための礎となるでしょう。
まとめ

機密保持は「知らなかった」では済まされない、社会人の必須スキルです。
新入社員の今こそ、未公開情報はすべて機密と捉える、SNSや会話・公共空間での取り扱いに細心の注意を払う、誓約書と社内ルールを理解・遵守する。この基本を徹底することで、情報漏洩リスクをゼロに近づけ、信頼される人材への最短ルートを歩めます。
たった一度のミスがキャリアと企業価値を傷つけますが、正しい知識と行動はあなたの最大の防御です。今日から社内資料の持ち出し・画面表示・Wi‑Fi利用・発言内容を「機密前提」で見直し、安心して成果に集中できる環境を自分でつくりましょう。
機密保持を守ることは、あなたの市場価値とチームの信頼を守ること。次は、社内の情報セキュリティポリシーと誓約書の再確認から一歩を踏み出してください。






