新入社員のみなさん、そろそろ会社にも慣れてきて、残業をすることも増えているのではないでしょうか。
しかし、この「残業」は自由にできるものではありません。
残業が認められているのは、「36協定」が締結されているからなのです。
今回は、その「36協定」について、わかりやすく紹介します。
知っておこう 残業のこと
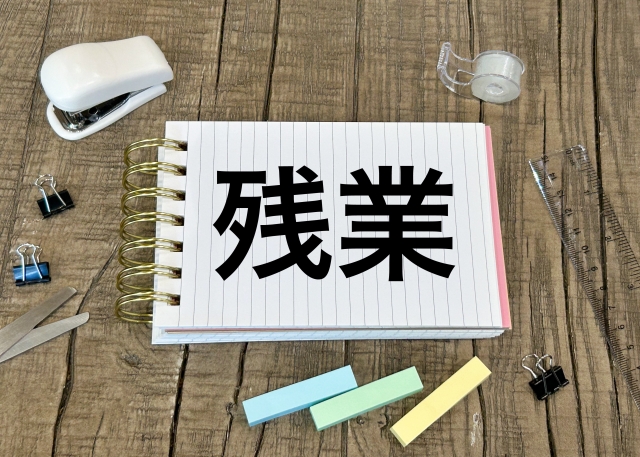
基本的に、残業の判断を従業員が自己判断で行うことは推奨されていません。また、会社によっては禁止している場合もあります。
残業するには「会社の指示・許可」が必要
多くの会社では、残業は事前申請・承認制となっています。これは以下の目的によるものです。
- 労働時間管理の適正化:会社には、従業員の労働時間を正確に把握する義務があります。自己判断での残業を認めてしまうと、正確な労働時間の管理が難しくなったり、必要のない時間まで残業してしまう恐れがあります。
- 人件費の管理:残業代は会社のコストに直結するため、無駄な残業を抑制し、人件費を適切に管理する必要があります。
- 労働者の健康管理:無計画な残業は労働者の健康を害する恐れがあるため、会社が残業時間を把握・管理することで過重労働を防止します。
- 36協定の遵守:36協定で定められた残業時間の上限を守るためにも、会社が残業を管理する必要があります。
上司から「残業をしてほしい」と言われたら?
上司から「残業をして欲しい」と明確に指示された場合、それは会社からの正式な業務命令とみなされます。この指示に基づいて働いた時間は、労働時間となり、当然ながら残業代(割増賃金)の支払い対象となります。
勝手に残業申請をした場合はどうなる?
就業規則に「残業は上司の許可を得て行うものとする」といった規定がある場合、必ず許可が必要です。許可なく残業した場合、残業代が支払われない可能性や、就業規則違反として懲戒の対象となる可能性もあります。
36協定って何?

「36協定」とは、正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法第36条に定められているため、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
これは、会社が従業員に法定労働時間を超えて残業をさせたり、法定休日に働かせたりする場合に、労働者の代表(または労働組合)と会社が話し合い、書面で取り交わす約束事のことです。
この36協定を会社と従業員の間で締結し、労働基準監督署に届け出ることで、会社は合法的に従業員へ残業を依頼できるようになります。
36協定は法定労働時間の遵守と例外の明確化
労働基準法では、原則として労働時間は「1日8時間」「1週間40時間まで」と定められています。
これを超えて働かせることや、法定休日に労働させることは法律違反となります。
しかし、現実的には業務の性質上、繁忙期や緊急時などに一時的な残業や休日出勤が必要となる場合もあります。
36協定は、このような例外的な場合に限り、労働者と使用者が書面で合意し、労働基準監督署に届け出ることで、合法的に時間外労働や休日労働を可能にする仕組みです。
36協定がないとどうなるの?
従業員に残業をさせることはできません!もちろん、新入社員のみなさんも対象です。
36協定が締結されていない場合、会社は原則として法定労働時間を超えて働かせることができません。
もし36協定なしに残業や休日出勤をさせた場合、会社は法律違反(罰則付き)となります。
36協定があれば無制限に残業OKなの?
「じゃあ、36協定さえあれば、いくらでも残業させられるの?」
そうではありません。無制限に残業させることはできません。
原則として、残業時間の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。
残業時間の上限は「1か月45時間」「1年360時間」
この時間を超えて残業させることは原則としてできない
もし超過させた場合、会社は法律違反となり、罰則の対象となる
ただし、「特別条項付き」の36協定を締結すれば、繁忙期など一時的にこの上限を超えることも可能です。
「特別条項付き」の36協定とは?
特別な事情がある場合には、労使の合意のもとで一時的に上限を超えることができる「特別条項付き36協定」を結ぶことができます。
【例えば】
- 突発的なトラブル発生(システム障害・機械故障など)
- 大規模なクレーム対応(多くの顧客に影響が及ぶ緊急対応)
- 予期せぬ受注増(大量の注文が突然入り、納期が迫っている場合。災害・感染症による生産遅延の回復など)
- 決算期などの繁忙期(年間のうち特に業務が集中する時期。あらかじめ予測できる場合でも「特別な事情」として認められることがある)
- イベントや大規模プロジェクトの最終段階
「特別条項付き」でも、無制限に残業できるわけじゃない!

特別条項があるからといって、好きなだけ残業してよいわけではありません。
むしろ、厳しい特別なルールが定められています。
残業できる回数に制限がある
1年のうち6か月まで、上限を超えて残業することが認められています。
つまり、毎月上限を超えて残業できるわけではありません。
年間・月間の上限がある
- 年間720時間以内(休日労働は含まず)
- 1か月100時間未満(休日労働を含む)
- 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均が80時間以内(休日労働を含む)
これらの上限を超えて残業させてしまうと、会社は法律違反となり、罰則の対象となります。
新入社員のみなさんはこの2つを知っておこう!

入社したてのみなさんは覚えることが沢山あるので、まずはこの2つを知っておきましょう。
会社は「36協定」を結んでいるか?
会社は、36協定を締結していなければ、みなさんに残業をさせることはできません。
入社後に残業を頼まれた場合は、「36協定が結ばれているかどうか」を必ず確認しましょう。
ほとんどの会社では労使間で締結されていますが、万が一結んでいなかったり、有効期限が切れていたりする場合もありますので注意が必要です。
36協定があっても「残業時間には上限」がある!
会社から「残業、残業」と言われ、長時間働かされていると感じたり、体調に異変を感じた場合は、迷わず上司・人事部・または会社の相談窓口に相談しましょう。
まとめ

今回紹介した「36協定」は、社員を守るための大切なルールです。
基本となる「36協定」の内容と、「特別条項付き」の上限ルールについて解説しました。
簡単にまとめると、
- 36協定がなければ、原則として残業や休日出勤はできない
- 36協定を結んでいても上限あり(※月45時間、年360時間など)
- 会社と労働者代表の間で締結し、労基署に届け出る必要あり
- 「特別条項付き」の場合は、月100時間未満、年720時間以内、複数月平均80時間以内という厳しい上限が設けられている
- 新入社員ももちろん対象
また、36協定は上限を明確に定めることで、労働者の過重労働を防止し、健康を守る役割も果たしています。
不明な点があれば、上司や人事部に気軽に確認してみましょう。
仕事も大切ですが、健康が何よりも大事です!






